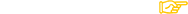処方構成(この漢方方剤を構成する生薬の組み合わせ)
| 生薬名 | 原材料と加工法 |
|---|---|
| 檳榔びんろう | ヤシ科ビンロウ属ビンロウの成熟種子 |
| 大黄だいおう | タデ科ダイオウ属のショウヨウダイオウ、タングートダイオウ、バテイダイオウなどの根茎 |
| 厚朴こうぼく | モクレン科モクレン属のカラホウ、オウヨウコウボク、ホウノキなどの樹皮 |
| 桂枝けいし | クスノキ科ニッケイ属ケイの細枝またはその樹皮 |
| 甘草かんぞう | マメ科カンゾウ属のウラルカンゾウおよび同属植物の根・走出茎 |
| 木香もっこう | キク科トウヒレン属モッコウの根 |
| 橘皮きっぴ | ミカン科ミカン属のウンシュウミカン、コウジ、タンジェリン、コベニミカンおよび同属植物の成熟果皮 |
| 蘇葉そよう | シソ科シソ属シソの葉 |
| 生姜しょうきょう | ショウガ科ショウガ属ショウガの根茎 |
| 呉茱萸ごしゅゆ | ミカン科ゴシュユ属のゴシュユおよびホンゴシュユの成熟前の果実 |
| 茯苓ぶくりょう | 外層を取り除いたサルノコシカケ科ウォルフィポリア属マツホドの菌核 |
適応疾患および対象症状
脚気、脚のむくみ、脚のしびれ、脚の冷え、脚の痛み、こむら返り、運動障害、関節の腫れ、胸苦しさ、悪心、嘔吐、悪寒、発熱、頭痛、憂鬱感、不安感、動悸、息切れ、呼吸困難、みぞおちのつかえ、倦怠感、腹部膨満感、便秘
薬理作用
浮腫改善、止嘔作用、消腫作用、感覚改善、冷感改善、鎮痛作用、止痙作用、呼吸改善、嘔気改善、運動改善、悪寒改善、解熱作用、抑鬱改善、精神安定、動悸改善、腹満改善、通便作用、元気回復、疲労回復
東洋医学的弁証(この方剤が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
寒湿脚気(寒湿による脚気)、下腿浮腫(下腿のむくみ)、悪心嘔吐(胃の気の逆流による吐き気や嘔吐)、感寒湿毒(寒湿の毒を受けている)、脚気腫満(脚気による腫れと膨満感)、心腹痞積(胸や腹部のつかえとしこり)、満悶短気(胸のつかえ感と息切れ)、気血凝滞(気と血の流れが滞り痛みが生じる)、脚気衝心(脚気が心臓を圧迫する)
治法・治療原則(この方剤が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
宣下寒湿(寒湿を下に宣発)、行気降濁(気を巡らせ濁を降ろす)、降逆止嘔(逆上を降ろし嘔吐を止める)、祛湿化濁(湿を除去し濁を化解)、温散寒湿(寒湿を温め散らす)、舒筋活絡(筋を舒り絡を活かす)、行気開壅(気を巡らせ閉塞を開放)
- 『方剤種別』については、複数の漢方方剤種別に属する方剤もあるが、当該方剤の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方方剤種別に基づき、単一の方剤種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該方剤が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この方剤の持つ「薬理作用」』については、当該方剤の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。