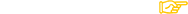処方構成(この漢方方剤を構成する生薬の組み合わせ)
適応疾患および対象症状
悪心、嘔吐、つわり、みぞおちのつかえ、みぞおちの痛み、動悸、めまい、口渇、急性胃炎、急性腸炎、胸膜炎、むくみ、脚気、蓄膿症
薬理作用
嘔気改善、止嘔作用、鎮痛作用、動悸改善、目眩改善、消炎作用、止渇作用、浮腫改善、去痰作用、消腫作用
東洋医学的弁証(この方剤が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
痰飲内停(痰飲が体内に停滞し咳やめまいが生じる)、胃気上逆(胃気が上逆する)、悪心嘔吐(胃の気の逆流による吐き気や嘔吐)、心下痞満(心下が痞え満ちる)、心悸眩暈(動悸とめまい)、胃脘冷痛(胃の冷えと痛み)、脚気水腫(脚気によるむくみ)
治法・治療原則(この方剤が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
降逆和胃(逆上を降ろし胃を和らげる)、温胃止嘔(胃を温め嘔吐を止める)、温胃散寒(胃を温め寒邪を散らす)、祛痰止痛(痰を除去し痛みを止める)、引水下行(水を引き下ろす)、化痰滌飲(痰を化し飲邪を洗い流す)
- 『方剤種別』については、複数の漢方方剤種別に属する方剤もあるが、当該方剤の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方方剤種別に基づき、単一の方剤種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該方剤が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この方剤の持つ「薬理作用」』については、当該方剤の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。