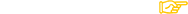異称別名および炮製品名
基原炮製(この生薬の原材料と加工法)
外層を取り除いた内部が白色のサルノコシカケ科ウォルフィポリア属マツホドの菌核
適応疾患および対象症状
尿量減少、むくみ、食欲不振、元気がない、腹鳴、腹部膨満感、泥状便、下痢、悪心、嘔吐、めまい、不眠、不安感、驚きやすい、動悸、もの忘れ、多痰、せきなど
薬理作用
浮腫改善、精神安定、尿量改善、食欲増進、利尿作用、元気回復、止瀉作用、腹鳴改善、消腫作用、腹満改善、便通改善、止嘔作用、嘔気改善、痴呆改善、睡眠改善、目眩改善、動悸改善、去痰作用、鎮咳作用など
東洋医学的弁証(この生薬が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
水湿壅盛(水湿が盛んに壅滞する)、水腫脹満(むくみや腹部の張り)、小便不利(小便が出にくい)、湿困脾胃(湿が脾胃を困らせる)、食少泄瀉(食欲不振と下痢が同時に起こる)、悪心嘔吐(胃の気の逆流による吐き気や嘔吐)、心神不寧(心神が落ち着かない)、驚悸失眠(驚きやすく眠れない)、迷惑健忘(物忘れがひどい状態)
治法・治療原則(この生薬が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
利水滲湿(水を利し湿邪を滲出)、健脾補中(脾を健やかにし中を補う)、寧心安神(心を寧め神を安ず)、健脾化痰(脾を健やかにし痰を転化)、補脾益心(脾を補い心を益す)
帰属経絡(この生薬が主に治療効果を発揮する、経絡および臓腑)
心、脾、胃、肺、腎
この生薬を用いる「漢方方剤」
| 方剤名 | 出典(処方来源) |
|---|---|
| 解酲湯かいていとう | 《脈因証治》みゃくいんしょうち |
| 葛花解酲湯かっかかいていとう | 《内外傷弁惑論》ないがいしょうべんわくろん |
| 葛花解酲湯かっかかいていとう | 《脾胃論》ひいろん |
| 枳実消痞丸きじつしょうひがん | 《蘭室秘蔵》らんしつひぞう |
| 啓脾丸けいひがん | 《万病回春》まんびょうかいしゅん |
| 健脾丸けんぴがん | 《証治準縄》しょうちじゅんじょう |
| 三痺湯さんぴとう | 《婦人大全良方》ふじんたいぜんりょうほう |
| 失笑丸しっしょうがん | 《蘭室秘蔵》らんしつひぞう |
| 実脾飲じっぴいん | 《済生方》さいせいほう |
| 実脾散じっぴさん | 《済生方》さいせいほう |
| 大七気湯だいしちきとう | 《三因極一病原論粋》さんいんきょくいちびょうげんろんすい |
| 二陳湯にちんとう | 《和剤局方》わざいきょくほう |
| 半夏茯苓天麻湯はんげぶくりょうてんまとう | 《衛生宝鑑》えいせいほうかん |
| 布袋丸ほていがん | 《補要袖珍小児方論》ほようゆうちんしょうにほうろん |
この生薬を用いる「漢方方剤」(異称別名表記)
| 方剤名 | 出典(処方来源) |
|---|---|
| 瓊玉膏けいぎょくこう | 《洪氏集験方》こうししゅうけんほう |
- 『生薬種別』については、複数の漢方生薬種別に属する生薬もあるが、当該生薬の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方生薬種別に基づき、単一の生薬種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該生薬が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この生薬の持つ「薬理作用」』については、当該生薬の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。