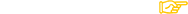異称別名および炮製品名
基原炮製(この生薬の原材料と加工法)
アケビ科アケビ属アケビの蔓性の茎
適応疾患および対象症状
焦燥感、不眠、口内炎、排尿痛、排尿障害、尿量減少、下腿痛、無月経、乳汁分泌不全、関節の痛み、運動障害、眼の充血、血尿、黄色いおりもの、脚気など
薬理作用
精神安定、利尿作用、鎮痛作用、睡眠改善、乳汁分泌、消炎作用、運動改善、月経改善、尿量改善、帯下改善、浮腫改善、消腫作用、止血作用など
東洋医学的弁証(この生薬が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
湿熱内蘊(湿熱が内に蘊蓄する)、心煩不眠(心が煩わしく眠れない)、小便不利(小便が出にくい)、脚気水腫(脚気によるむくみ)、瘀血阻滞(瘀血が気血の流れを阻害し痛みが生じる)、経閉黄帯(無月経と黄色いおりもの)、熱淋渋痛(熱淋で渋痛する)、乳汁不下(乳汁の分泌不足)、湿熱痺証(湿熱による関節痛)
治法・治療原則(この生薬が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
清熱利湿(熱を清め湿を利す)、通気下乳(気を通し乳汁を下げる)、利水通淋(水を利し淋を通す)、宣通通経(宣発させ経絡を通す)、心火清降(心の火を清め降ろす)、通利関節(関節を通利にする)、降火利水(火を降ろし水を利する)、通利小便(小便を通じ利する)
帰属経絡(この生薬が主に治療効果を発揮する、経絡および臓腑)
心、小腸、膀胱
この生薬を用いる「漢方方剤」(異称別名表記)
| 方剤名 | 出典(処方来源) |
|---|---|
| 甘露消毒丹かんろしょうどくたん | 《医効秘伝》いこうひでん |
| 橘核丸きっかくがん | 《済生方》さいせいほう |
| 五淋散ごりんさん | 《万病回春》まんびょうかいしゅん |
| 小薊飲子しょうけいいんし | 《済生方》さいせいほう |
| 消風散しょうふうさん | 《外科正宗》げかせいそう |
| 宣毒発表湯せんどくはっぴょうとう | 《医宗金鑑》いそうきんかん |
| 疏鑿飲子そさくいんし | 《済生方》さいせいほう |
| 通導散つうどうさん | 《万病回春》まんびょうかいしゅん |
| 導赤散どうせきさん | 《小児薬証直訣》しょうにやくしょうちょくけつ |
| 導赤清心湯どうせきせいしんとう | 《重訂通俗傷寒論》じゅうていつうぞくしょうかんろん |
| 八正散はっしょうさん | 《和剤局方》わざいきょくほう |
| 普済解毒丹ふさいげどくたん | 《温熱経緯》おんねつけいい |
| 竜胆瀉肝湯りゅうたんしゃかんとう | 《一貫堂方》いっかんどうほう |
| 竜胆瀉肝湯りゅうたんしゃかんとう | 《医方集解》いほうしゅうかい |
| 竜胆瀉肝湯りゅうたんしゃかんとう | 《校注婦人良方》こうちゅうふじんりょうほう |
- 『生薬種別』については、複数の漢方生薬種別に属する生薬もあるが、当該生薬の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方生薬種別に基づき、単一の生薬種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該生薬が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この生薬の持つ「薬理作用」』については、当該生薬の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。