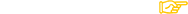異称別名および炮製品名
基原炮製(この生薬の原材料と加工法)
キク科オケラ属のホソバオケラおよびシナオケラの根茎
適応疾患および対象症状
身体の痛み、むくみ、脚の無力感、関節の痛み、関節の腫れ、脚の痛み、腰痛、腹部膨満感、食欲不振、胸苦しさ、悪心、嘔吐、下痢、頭痛、無汗、発熱、悪寒、視神経萎縮、中心性網膜炎、視力低下、角膜の混濁、白内障など
薬理作用
鎮痛作用、視力改善、浮腫改善、筋力向上、消腫作用、発汗作用、腹満改善、止嘔作用、食欲増進、止瀉作用、嘔気改善、解熱作用、悪寒改善、消炎作用など
東洋医学的弁証(この生薬が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
風寒湿痺(風寒湿の邪気が関節に侵入し痛みやしびれを起こす)、湿熱痺証(湿熱による関節痛)、肢体酸痛(手足のだるい痛み)、湿困脾胃(湿が脾胃を困らせる)、外感風寒(外部からの風邪と寒邪による感冒症状)、夜盲青盲(夜盲症と視力障害)、目生翳障(目に翳ができる)、嘔吐腹満(嘔吐と腹部の張り)、関節腫痛(関節が腫れ痛む)
治法・治療原則(この生薬が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
祛風除湿(風を除き湿を取り除く)、燥湿健脾(湿を燥させ脾を健やかにする)、解表散寒(体表を解放し寒邪を散らす)、除障明目(障害を除去し目を明るく)、発汗解表(発汗させ体表を解放)、祛風止痛(風邪を除去し疼痛を止める)
帰属経絡(この生薬が主に治療効果を発揮する、経絡および臓腑)
脾、胃
この生薬を用いる「漢方方剤」
| 方剤名 | 出典(処方来源) |
|---|---|
| 胃苓湯いれいとう | 《丹渓心法》たんけいしんぽう |
| 越鞠丸えつぎくがん | 《丹渓心法》たんけいしんぽう |
| 葛根加朮附湯かっこんかじゅつぶとう | 《吉益東洞方》よしますとうどうほう |
| 芎朮丸きゅうじゅつがん | 《丹渓心法》たんけいしんぽう |
| 九味羗活湯くみきょうかつとう | 《此事難治》しじなんち |
| 桂枝加朮附湯けいしかじゅつぶとう | 《吉益東洞方》よしますとうどうほう |
| 桂枝加苓朮附湯けいしかりょうじゅつぶとう | 《吉益東洞方》よしますとうどうほう |
| 五加減正気散ごかげんしょうきさん | 《温病条弁》おんびょうじょうべん |
| 五積散ごしゃくさん | 《和剤局方》わざいきょくほう |
| 柴平湯さいへいとう | 《増補内経拾遺方論》ぞうほだいけいしゅういほうろん |
| 三妙丸さんみょうがん | 《医学正伝》いがくしょうでん |
| 三妙丸さんみょうがん | 《成方便読》せいほうべんどく |
| 三妙散さんみょうさん | 《羅氏会約医鏡》らしかいやくいきょう |
| 四妙丸しみょうがん | 《成方便読》せいほうべんどく |
| 消風散しょうふうさん | 《外科正宗》げかせいそう |
| 清上蠲痛湯せいじょうけんつうとう | 《寿世保元》じゅせいほげん |
| 清暑益気湯せいしょえっきとう | 《脾胃論》ひいろん |
| 蒼朮散そうじゅつさん | 《世医得効方》せいとくこうほう |
| 蒼柏二妙丸そうはくにみょうがん | 《症因脈治》しょういんみゃくち |
| 疎経活血湯そけいかっけつとう | 《万病回春》まんびょうかいしゅん |
| 大羗活湯だいきょうかつとう | 《此事難治》しじなんち |
| 治頭瘡一方ちずそういっぽう | 《本朝経験方》ほんちょうけいけんほう |
| 当帰拈痛湯とうきねんつうとう | 《医学啓源》いがくけいげん |
| 二妙丸にみょうがん | 《丹渓心法》たんけいしんぽう |
| 二妙散にみょうさん | 《丹渓心法》たんけいしんぽう |
| 拈痛湯ねんつうとう | 《蘭室秘蔵》らんしつひぞう |
| 半夏白朮天麻湯はんげびゃくじゅつてんまとう | 《脾胃論》ひいろん |
| 半夏茯苓天麻湯はんげぶくりょうてんまとう | 《衛生宝鑑》えいせいほうかん |
| 半朮天麻湯はんじゅつてんまとう | 《簡明医彀》かんめいいこう |
| 白虎加蒼朮湯びゃっこかそうじゅつとう | 《類証活人書》るいしょうかつじんしょ |
| 不換金正気散ふかんきんしょうきさん | 《和剤局方》わざいきょくほう |
| 平胃散へいいさん | 《和剤局方》わざいきょくほう |
| 陽明二妙丸ようめいにみょうがん | 《症因脈治》しょういんみゃくち |
| 薏苡仁湯よくいにんとう | 《明医指掌》みんいししょう |
| 陽明二妙丸陽明にみょうがん | 《症因脈治》しょういんみゃくち |
- 『生薬種別』については、複数の漢方生薬種別に属する生薬もあるが、当該生薬の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方生薬種別に基づき、単一の生薬種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該生薬が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この生薬の持つ「薬理作用」』については、当該生薬の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。