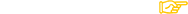異称別名および炮製品名
基原炮製(この生薬の原材料と加工法)
外皮を除いたウリ科カラスウリ属のシナカラスウリおよびキカラスウリなどの塊根
適応疾患および対象症状
口渇、尿量過多、空咳、喀血、皮膚化膿症など
薬理作用
止渇作用、鎮咳作用、尿量改善、止血作用、消腫作用、皮膚再生、排膿作用、解毒作用など
東洋医学的弁証(この生薬が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
熱病傷津(熱病で津液が損傷する)、口渇煩躁(口渇と焦燥感)、消穀善飢(穀を消しよく飢える)、肺熱咳嗽(肺の熱による咳)、乾咳喀血(乾いた咳と喀血)、癰瘡腫毒(化膿性の皮膚病変)
治法・治療原則(この生薬が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
清熱生津(熱を清め津液を生じる)、潤燥止渇(燥を潤し渇きを止める)、清肺潤燥(肺を清め燥を潤す)、消腫排膿(腫れを消し膿を排す)、潤肺化痰(肺を潤し痰を化す)、解毒消腫(毒を解し腫れを消す)、清熱化痰(熱を清め痰を化す)、潤肺止咳(肺を潤し咳を止める)、養胃生津(胃を養い津液を生じる)
帰属経絡(この生薬が主に治療効果を発揮する、経絡および臓腑)
肺、胃
この生薬を用いる「漢方方剤」
この生薬を用いる「漢方方剤」(異称別名表記)
| 方剤名 | 出典(処方来源) |
|---|---|
| 姜桂湯きょうけいとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 柴胡姜桂湯さいこきょうけいとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 柴胡桂姜湯さいこけいきょうとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 柴胡桂枝乾姜湯さいこけいしかんきょうとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 柴胡桂枝乾姜湯さいこけいしかんきょうとう | 《金匱要略方論》きんきようりゃくほうろん |
| 柴胡清肝湯さいこせいかんとう | 《一貫堂方》いっかんどうほう |
| 柴胡白虎湯さいこびゃっことう | 《重訂通俗傷寒論》じゅうていつうぞくしょうかんろん |
| 神犀丹しんさいたん | 《温熱経緯》おんねつけいい |
| 真人活命飲しんじんかつめいいん | 《証治準縄》しょうちじゅんじょう |
| 真人活命飲しんじんかつめいいん | 《校注婦人良方》こうちゅうふじんりょうほう |
| 真人活命飲しんじんかつめいいん | 《医方集解》いほうしゅうかい |
| 仙方活命飲せんぽうかつめいいん | 《校注婦人良方》こうちゅうふじんりょうほう |
| 仙方活命飲せんぽうかつめいいん | 《医方集解》いほうしゅうかい |
| 仙方活命飲せんぽうかつめいいん | 《証治準縄》しょうちじゅんじょう |
| 復元活血湯ふくげんかっけつとう | 《医学発明》いがくはつめい |
- 『生薬種別』については、複数の漢方生薬種別に属する生薬もあるが、当該生薬の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方生薬種別に基づき、単一の生薬種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該生薬が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この生薬の持つ「薬理作用」』については、当該生薬の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。