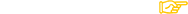異称別名および炮製品名
基原炮製(この生薬の原材料と加工法)
蒸して発酵させたマメ科ダイズ属ダイズの成熟種子
適応疾患および対象症状
発熱、悪寒、頭痛、無汗、ノドの痛み、胸苦しさ、不眠など
薬理作用
解熱作用、鎮痛作用、悪寒改善、発汗作用、睡眠改善、精神安定など
東洋医学的弁証(この生薬が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
風熱表証(風と熱による体表の症状)、風寒表証(風と寒さによる体表の症状)、頭痛発熱(頭痛と発熱)、発熱無汗(発熱があるが汗が出ない)、心胸煩悶(心胸が煩わしく悶える)、虚煩不眠(陰虚による不眠とイライラ)、邪熱内擾(邪熱が体内を乱す)
治法・治療原則(この生薬が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
疏散解表(散らし体表を解放)、宣鬱除煩(鬱を宣発し煩わしさを除く)、除煩調中(煩わしさを除き中焦を調節)
帰属経絡(この生薬が主に治療効果を発揮する、経絡および臓腑)
脾、胃
この生薬を用いる「漢方方剤」
| 方剤名 | 出典(処方来源) |
|---|---|
| 黄連黄芩湯おうれんおうごんとう | 《温病条弁》おんびょうじょうべん |
| 加減葳蕤湯かげんいずいとう | 《重訂通俗傷寒論》じゅうていつうぞくしょうかんろん |
| 活人葱豉湯かつじんそうしとう | 《類証活人書》るいしょうかつじんしょ |
| 枳実梔子豉湯きじつしししとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 銀翹散ぎんぎょうさん | 《温病条弁》おんびょうじょうべん |
| 香蘇葱豉湯こうそそうしとう | 《通俗傷寒論》つうぞくしょうかんろん |
| 三黄石膏湯さんおうせっこうとう | 《傷寒六書》しょうかんりくしょ |
| 梔子甘草豉湯ししかんぞうしとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 梔子豉湯しししとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 梔子生姜豉湯しししょうきょうしとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 石膏湯せっこうとう | 《外台秘要》げだいひよう |
| 桑杏湯そうきょうとう | 《温病条弁》おんびょうじょうべん |
| 葱豉桔梗湯そうしききょうとう | 《重訂通俗傷寒論》じゅうていつうぞくしょうかんろん |
| 葱豉湯そうしとう | 《肘後備急方》ちゅうごびきゅうほう |
| 葱白七味飲そうはくしちみいん | 《外台秘要》げだいひよう |
| 連朴飲れんぼくいん | 《霍乱論》かくらんろん |
この生薬を用いる「漢方方剤」(異称別名表記)
- 『生薬種別』については、複数の漢方生薬種別に属する生薬もあるが、当該生薬の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方生薬種別に基づき、単一の生薬種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該生薬が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この生薬の持つ「薬理作用」』については、当該生薬の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。