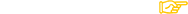異称別名および炮製品名
基原炮製(この生薬の原材料と加工法)
サルノコシカケ科チョレイマイタケ属チョレイマイタケの菌核
適応疾患および対象症状
尿量減少、むくみ、泥状便、おりものなど
薬理作用
浮腫改善、消腫作用、尿量改善、帯下改善、便通改善、止瀉作用、利尿作用、鎮痛作用、黄疸改善、頻尿改善、尿色改善など
東洋医学的弁証(この生薬が対象とする、東洋医学の診断に基づく疾患および症状)
水湿停滞(水湿が停滞する)、小便不利(小便が出にくい)、水腫脹満(むくみや腹部の張り)、泄瀉便溏(下痢と軟便)、白色帯下(白色のおりもの)、熱淋渋痛(熱淋で渋痛する)、湿熱黄疸(湿熱による黄疸)、頻尿尿濁(頻尿と濁った尿)
治法・治療原則(この生薬が持つ、東洋医学的治療法と治療原則)
利水滲湿(水を利し湿邪を滲出)、利水消腫(水を利し腫れを消す)、利水止瀉(水を利し下痢を止める)、清熱利湿(熱を清め湿を利す)
帰属経絡(この生薬が主に治療効果を発揮する、経絡および臓腑)
腎、膀胱
この生薬を用いる「漢方方剤」(異称別名表記)
| 方剤名 | 出典(処方来源) |
|---|---|
| 胃苓湯いれいとう | 《丹渓心法》たんけいしんぽう |
| 茵蔯五苓散いんちんごれいさん | 《金匱要略方論》きんきようりゃくほうろん |
| 黄芩滑石湯おうごんかっせきとう | 《温病条弁》おんびょうじょうべん |
| 解酲湯かいていとう | 《脈因証治》みゃくいんしょうち |
| 藿朴夏苓湯かくぼくかりょうとう | 《医原》いげん |
| 葛花解酲湯かっかかいていとう | 《内外傷弁惑論》ないがいしょうべんわくろん |
| 葛花解酲湯かっかかいていとう | 《蘭室秘蔵》らんしつひぞう |
| 葛花解酲湯かっかかいていとう | 《脾胃論》ひいろん |
| 滑石藿香湯かっせきかっこうとう | 《温病条弁》おんびょうじょうべん |
| 桂苓甘露飲けいりょうかんろいん | 《宣明論方》せんめいろんぽう |
| 桂苓甘露散けいりょうかんろさん | 《宣明論方》せんめいろんぽう |
| 桂苓白朮散けいりょうびゃくじゅつさん | 《宣明論方》せんめいろんぽう |
| 五苓散ごれいさん | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 五苓散ごれいさん | 《金匱要略方論》きんきようりゃくほうろん |
| 柴苓湯さいれいとう | 《世医得効方》せいとくこうほう |
| 春沢湯しゅんたくとう | 《医方集解》いほうしゅうかい |
| 四苓散しれいさん | 《丹渓心法》たんけいしんぽう |
| 宣清導濁湯せんせいどうだくとう | 《温病条弁》おんびょうじょうべん |
| 猪苓湯ちょれいとう | 《傷寒論》しょうかんろん |
| 猪苓湯ちょれいとう | 《金匱要略方論》きんきようりゃくほうろん |
| 猪苓湯合四物湯ちょれいとうごうしもつとう | 《本朝経験方》ほんちょうけいけんほう |
| 当帰拈痛湯とうきねんつうとう | 《医学啓源》いがくけいげん |
| 二宜丸にぎがん | 《類編朱氏集験医方》るいへんしゅししゅうけんいほう |
| 拈痛湯ねんつうとう | 《蘭室秘蔵》らんしつひぞう |
| 分消湯ぶんしょうとう | 《万病回春》まんびょうかいしゅん |
| 理苓湯りれいとう | 《張氏医通》ちょうしいつう |
- 『生薬種別』については、複数の漢方生薬種別に属する生薬もあるが、当該生薬の薬理作用が最も顕著にあらわれる漢方生薬種別に基づき、単一の生薬種別に属させている。
- 『東洋医学的弁証』および『治法・治療原則』については、中医用語に精通していない一般の方を考慮し、あえて重複表現を一部用いている。
- 『適用疾患および対象症状』については、当該生薬が直接的に効力を示す疾患・症状に加え、間接的に効力を示す疾患・症状についても併記している。
- 『この生薬の持つ「薬理作用」』については、当該生薬の直接的な薬理作用に加え、間接的な薬理作用についても併記している。